�ב���Ǝs�����̐����o�ϊw�i�h�j
�@�@�@�@�j�N�\����V���b�N����Ζ���@�O��܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@��
�͂��߂�
�@�ב���Ƃ́A���O�ύt���ێ����A�o�ϐ�����ʂ��č����̌o�ό����̋ɑ剻��Nj����鐭��̈�Ƃ��āA�����Ȃ�ב֑��ꐧ�x��I�����^�c���邩�Ƃ������ւ̎�g�݂ł���A�f�Ր������Z����ƂƂ��ɐ��i�����B�����Ĉב֎s��ւ̒ʉݓ��ǂ̉��[1]�́A�ב���̋�̓I�Ȕ����̈�`�ԂƂ����悤�B
�u���g���E�b�Y�̐��̉��ł́C�o�^���ꂽ�h�l�e�����𒆐S�Ɉ��͈͓̔��Ɉב֑�����ێ����邽�߂Ɏs�����������Ȃ�ꂽ�B�ϓ��ב֑��ꐧ�̉��ł́A�ב֑���̓t�@���_�����^���Y�f���ď_��ɕϓ����ׂ����̂ł���[2]�A�ʉݓ��ǂɂ��s�����͓��@�I�ȓ����ȂǂŐ�����}���Ȉב֑���̕ϓ���}�����邽�߂ɍs����Ƃ���Ă���[3]�B����ł͈ב֎s�����͗�O�I�ɍs���Ă����̂��낤���B�����ɂ́A�ϓ��ב֑�����̉���z�́A�u���g���E�b�Y�̐����̉���z���������Ƃ����w�E������[4]�B
���̒��ŁA�{�M�̒ʉݓ��ǂ́A���݂Ɏ���܂ŁA���̐�i���ł͌����Ȃ���K�͂Ȉב֎s�������p�����Ă����B�����N�ȍ~��Z�Z�O�N�㌎�܂ł̉���z�̗v�ł́A�h�����襉~��������ܒ��~�ł���̂ɑ��āC�h�������E�~����͎l�Z���~�O��ň��|�I�ɉ~���U���A�������͉~���}�~�̎p�����ǂݎ���B
��Z�Z�O�N�ɓ����Ă�����A��`�㌎�Ɉ�O���~�̉~�����������{�����B�܊p�̉肪�o�n�߂����{�o�ςɃu���[�L��������~����������邱�Ƃ́C�P�ɓ��{�̗��v�݂̂Ȃ炸�A���ۓI�ɂ��������ꂤ��Ƃ���{�M���ǂ̎咣�ɂ������āA������ʂ��^�⎋�������������A�܂��A�o�哱�̌o�ϐ����H����E������Ȃ�������Гh������̂Ƃ̔ᔻ���������B�����ĉ���̌��ʁA�c��オ�����O�ݏ����́A��Z�Z�O�N�㌎�ɂ͘Z�牭�h����˔j�����B��ɕč��̒Z�������ȏ،��ɉ^�p����Ă���B�č������ȏ،��̊C�O�ۗL�̔�d�����܂��Ă���C�Z�����ɂ͖�꒛�l�牭�h���A�䗦�ɂ��ĎO�ܥ�Z���ƂȂ��Ă��邪�A�����O�������{�ɂ��ۗL����Ă���[5]�B�בփ��X�N������A�������܂܂Ȃ��
���Y���K�͂ɐςݏグ��ُ͈̂킾�Ƃ��������������B
�܂�����ɕK�v�ȉ~�����͊O���ב֎������ʉ�v�ɂ�蔭�s����鐭�{�Z���،��Œ��B����邪�A���̎c��������c���������(�Z�O�N�x�͎��㒛�~)�ɋ߂Â��Ă���C����Ȃ�~�������̂��߂ɂ͑��g���K�v�ł���B�č��̍����Ԏ��̃t�@�C�i���X�𑊓����x���{�������s�����Ęd���\�}�ƂȂ��Ă��邪�A����܂ō���ł����̑Ó����ɂ��ď\���ȋc�_������Ă��Ȃ����A�ʉݓ��ǂ��\���Ȑ����ӔC���ʂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
�ב֑���͓Ԃ̒ʉ݂̌����䗦�ł���ȏ�C�ב֑���̐����ɑ��Ă��鍑�̒ʉݓ��ǂ��e���͂��s�g���邱�Ƃ́C���荑�Ƃ̊Ԃɑ��݂���o�ϥ���Z�W�݂̂Ȃ炸������O���W�֗l�X�ȉe���������炷�\��������B�܂�����珔�W���A�ʉݓ��ǂ̉��������K�肷�邩������Ȃ��B�Ƃ��Ƀh���~����̂悤�ɁA���E�o�ς̒��ŏd�v�Ȓn�ʂ��߂Ă���̒ʉ݂��W����ꍇ�ɂ́C�������͍��ې����o�Ϗ�̏d��Ȗ��ɂȂ肤��B
����ɍ����̗l�X�ȍs��̂ɑ���e�����傫���B�~���U���͗A�o�Y�Ƃ��������C�A���Y�ƁA�����ď���҂ɂƂ��Ă͑Ō��ƂȂ肤��B�ב֎s�����́A�����̍ĕ��z���ʂ����ȏ�C�o�ϓI���ʂɉ����Đ����I�Ȍ��ʂւ̔z���͕s���Ȕ��ł���B�ʉݓ��ǂֈב։����C���Ă��鐭���}�Ƃ̊Ԃɂ́A�ǂ̂悤�Ȏ����I�ϔC�W�����݂��A�㗝�l����ʉݓ��ǂ̍s���̗U���������͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�����ӔC����]���͂ǂ̂悤�Ɏ��s�����̂��ȂǑ����̋^�₪����B�c�O�Ȃ��炱���ɂ��Ă̐������ǂ̎���I�Ȑ������R�����A�f�[�^�̌��\���ŏ����Ɏ~�܂��Ă���̂�����ł���B�]���ĊO���҂́A����ꂽ�������ƂɁC�ʉݓ��ǂ̈Ӑ}�����߂��C�]������������Ȃ��B
���̂悤�Ȗ��ɑ��āC�����҂����́A��Ƃ��Čv�ʓI�ȃA�v���[�`�ɂ���ĉ���̌��ʂɂ��Ă̕��͂ƕ]�����s���Ă���[6]�B�������Ȃ���ב։������ɂ��Ă͍��ې����o�ς̉e���⍑���̏��o�ύs��̊Ԃ̑��ݍ�p���ώ@����͂̕K�v������A���̂��߂ɐ����o�ϊw�I�m�������p���邱�Ƃɂ��A���̖��̗�����[�߁A�o�ϊw�I�ȕ]���̎ړx�Ƃ͈قȂ鎋�_���ł��Ȃ����Ƃ����̂��A�{�e�̖��ӎ��ł���B
��@�ב֎s�����̌o�ϊw
�@���̖��ɂ��Đ����o�ϊw�I�Ȑڋ߂�}��ɂ��Ă��C����܂ł̌o�ϊw�I�ȕ��͂̐��ʂ܂���K�v�����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
��\��@�ב֎s��ւ̉���̌��ʂɂ���
�ב֎s��ւ̉���́A��s�ى�����ƕs�ى�����ɕ������C���ꂼ��̌��ʂ��r����`�ŋc�_����Ă���[7]�B
�i��j��s�ى�����F�ʉݓ��ǂ͍����̉ݕ��X�g�b�N�ɉe����^��������ňב֎s��ɉ������B�Ⴆ�Γ��₪�h�����j�~�̂��߁A�h��������~��������āA���Ԃɋ������ꂽ�~����u���ĉݕ��X�g�b�N�̑�����e�F����A���{�̋����͒ቺ�A�h�����Y�ɔ�ׂĉ~���Y�ۗL�̗U�����ቺ���悤�B�܂����Z�ɘa�Ő��Y���h������C�A�����������A�h������j�~�ł���B�����ő����̌o�ϊw�҂����́C���̎�̉���͈ב֑���ɉe������ƍl����B
�i��j�s�ى�����F�ב։���������ݕ��X�g�b�N�ɗ^����e�����C������s�����J�s�ꑀ��Ȃǂő��E����B���Y���s���S���[8]�ł���A�ב֑���ɉe����^�����邩������ʂ��A��ʂɂ͌��ʂ��Ȃ��Ƃ����̂��R���Z���T�X�ƂȂ��Ă���[9]�B
���Ƃ��Ζ{�M�ʉݓ��ǂ��h�����j�~�̕s�ى�����������ꍇ�C�������Z�s��@�@�ɕω��Ȃ��������ς��Ȃ���C���͂̂Ȃ��h�����Y���w������U���͍��܂�Ȃ��B���̉�����ב֑���ɉe����^����Ƃ���A�����ύX�ւ̃V�O�i���v�Ƃ��Ď~�߂���ꍇ�ł��낤�B�s��Q���҂��ʉݓ��ǂ͏������Z�����]�����A�t�@���_�����^���Y�̕ω������N����������Ȃ��Ɨ\�z����C���͈̔͂Ō��ʂ�����������Ȃ�[10]�B
��\��@���{�ɂ�����ŋ߂̘_��
�@
�����N�Ĉȍ~�}���ɉ~�����i�݁A��ʂ̃h������������s���Ă������C���Z�̗ʓI�ɘa�̈�̎�i�Ƃ��āC��s�ى���������߂�咣�����܂�C����������Ę_�������܂����B����܂ł̍����ȁi���呠�ȁj�̉������Ɠ���̑Ή��ɂ��Ă̕]����A���ꂩ��̋��Z������ב���̘g�g�݂Ɋւ���肪�_�����Ă���B
�i��j����s�ى������ᔻ
�l�c[��Z�Z�Z]�́A�ב։�����L���ł���̂́A�����̃}�l�[��T�v���C�̑��Δ䗦���ς�邩��ł���A����̕s�ى��ł���ʂ��ɂȂ�Ɣᔻ����[11]�B
�i��j���{[��Z�Z�Z]�A���E����[��Z�Z�Z]�́A���Z�s��ŗ��o�����鋐�z�Ȏ����ʂ��l����C�ב։�������͋͂��ł���C�s�ى����s�ى��̋�ʂ������I�łȂ����A�ב���̂��߂ɓ���̐���^�c��ύX����K�v�͂Ȃ��Ƃ��A�ނ��떳�����ȕs�ى�������Ă���[12]�B
�i�O�j���[��Z�Z�O]�́A����̐��Z�������ȂLjבֈȊO�̎w�W�𑀍�ڕW�Ƃ��Đ���^�c���s���Ă���̂ŁA����̔�s�ى��Ƃ͑��e��Ȃ��Ǝw�E�����A�בւ͍����Ȃ̐ӔC�Ƃ������̌��������������ł����A�ב֑���͓���̐����ύX�Œ������邵���Ȃ��Ƃ���B�����Ĉב֗U���̐��ۂ́u�s��Ɏx�z�I�ȗ\�z�v�������Ƃɂ������Ă���A�}�N������Ƃ��ɋ��Z����𐮍��I�ɉ^�c����ʉݓ��Ǒ��̋����R�~�b�g�����g���K�v�Ǝ咣����[13]�B�@
��@�ב���E�ב֎s�������ւ̐����o�ϊw�I�ڋ�
�@
�s��Ɏx�z�I�ȗ\�z��ω������Ȃ���A�ב։���̌��ʂ����҂ł��Ȃ��Ƃ���A�ʉݓ��ǂɂ��ב֥���Z����̉^�c�ɂ��āA�s��̐M�F���l�����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߂ɂ͂����̐��A���ې����o�ς̑傫�Șg�g�݂�A�����̏��s��̊Ԃ̗��Q�������������邽�߂̏�����Ƃ̊Ԃɑ傫�Ȗ����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̋^��������A�s��͈ב։�����₪�Ĕj�]���邱�Ƃ����z���C����I�I���������ב֓��@���������邱�ƂɂȂ�B
�o�ϊw�́A�O�q�̂悤�Ȑ����o�ϓI���ɂ��Ă͊O���I�ȗv���Ƃ��āC�l�@�̑ΏۂƂ��Ȃ��B����ł͈ב։������̗L��������蓥�ݍ���ŕ]�������ŁC�ǂ̂悤�ȗ��_���@������̂��낤���B
��\��@���ې����o�ϊW�l�@�̘g�g��
�i��j���Ƃƍ������s���
����̍��ې����o�ϊW�́A�g�傷�鑽���А��Y�A�����������Z�̗���A���R�����i�ލ��ۖf�Ղœ����t�����Ă���B�����Ɍl�C�W�c�C�K���C���ƊԂ̐����I���������債�Ă���B�o�ϓI�����̐i�W�ƕx�̐��Y�A�����I�x�z�⍑�Ƃ̎����ւ̗~�]�̑������A�O���[�o�������o�ςŔ������Ă��鑽���̌��ۂ��K�肷��B���G�ȍ��ې����o�ϖ������Ęg�g�݂����C���̒��Ɉב�����ʒu�t���邽�߂ɁA�������̍l�������������Ă݂悤�B
�t���[�f���ƃ��C�N[14]�́A�@���ۓI���́E�v�����A�����̐�����o�ς��K�肷��ꍇ�ƁA���̋t�̏ꍇ�̂ǂ�����d�����邩�A�A���ƂƎЉ�A���{�Ƃ��ꂪ��\���Ă���Љ�I���͂Ƃ̊W�A���Ȃ킿���Ƃ��Љ�I�����͂���Ɨ����ēƎ��̘_���ōs�����Ă��邩�A�Љ�I�����͂�P�ɑ�\���Ă���̂��Ƃ�����{�I�Ȏ��_����o������B
�@������̎��_��g�ݍ��킹��ƁA�l�̈قȂ�A�v���[�`�ɐ��������B
�i�P�j���ۓI�A�v���[�`
�@���ې����d���̌����F�����Ƃ��������Ă���n���w�I�A�O��I�Ȋ��ɂ���āA�����Ƃɉۂ���鐧����d������B
�A���یo�Ϗd���̌����F�ʍ��Ƃւ̊O������̐���̏d�v�����������邪�A�����I�v�����O���[�o���ȎЉ�o�ϓI�v���Ɍ��Ă�B�Z�p�C�ʐM�C���Z�A���Y�Ȃǂ���{�I�ɏ����Ɛ�������߂���ɉe������ƍl����B
(�Q)�����I�A�v���[�`
�@�������x�d���̌����F�����̐���҂���I���x���A���Ƃ̗D�揇�ʂ����肵����𐋍s����B�Љ�I�ȏ����͂��獑�Ƃ����������ێ����Ă���ꍇ������A���Ƒg�D����Ƃ��ĎЉ�I�����̗͂��Q�₷��@�\���d������ꍇ������B
�A�����Љ�d���̌����F�����̌o�ς�Љ���I�s��̂ɒ��ڂ��A���ۓI����v�������A�����̎Љ�o�ϓI�Ȉ��͂��d������B���̐���̌���v���́A�l�A��ƁA�W�c���̗v���ł���A����҂̓Ɨ������s���ł͂Ȃ��Ƃ���B
�ȏ�̂悤�ɒP�������ꂽ�A�v���[�`�ł́A�����̍��ې����o�ϊW�����j���A���X�╡�G��������ł��Ȃ��ɂ��Ă��A���鍑�̑ΊO�o�ϐ����ۓI�ƍ����I�A�����Đ����I�ƌo�ϓI�ȗv���ɂ�萧��Ă��邱�ƁA���鎞�_�C���鍑�ŁA����͂̑g�������A���̗͂̑g���������d�v�ł���Ƃ������ƁA���Ȃ킿�Љ�I�����͂��A�����I�ȍ��ƍs�����C�O���[�o���ȗv�����C�����v�������ώ@�����|����ƂȂ�B
(��)�@���ĊW�ɂ���
�@�ב���𐭎��o�ϊw�I�Șg�g�݂̒��Ŋώ@����ꍇ�C���ƊԂ̊W�A�Ƃ��ɓ��ĊW���ǂ̂悤�Ȏ��_���瑨���邩���d�v�ł���B
�@�i�P�j�p�N�X�E�A�����J�[�i
���Ă̈ב���̑�g�Ƃ��Ă̐��̍��ې����o�ϊW�ɂ��āA�����o�ϊw�͂ǂ̂悤�ȑ����Ă����������Č��悤�B
���̍��ۑ̐��́A��Ԋ��̍����Ȃ��������邽�߂̍��ۘA���哱�̏W�c���S�ۏ�̐��ƁA���ې����o�ϑ̐��Ƃ��Ẵu���g���E�E�b�Y�̐�����ՂƂ��č\�z���ꂽ�B������������킪��������ɂ�Đ��̐��͕ω����C�����͕č����S�̏W�c�h�q�Ԃ�z���A�u���g���E�b�Y�̐����܂��A�č��̌o�ϗ͂Ɉˑ����ċ@�\���邱�ƂɂȂ����B
�@���̂悤�ȓ����f���āC�����o�ϊw�ł́A�Z�Z�N��㔼���玵�Z�N��O���ɂ́A���ۊW�ɂ����鍑�����z�����o�ϖ��̏d�v�����������频��݈ˑ��_��A���Z�N��㔼���甪�Z�N��ɂ����Ă͍����̐��ƍ��ۊW�̈���𐧓x�������݈ˑ��W���Ǘ����悤�Ƃ���u���ۃ��W�[���_�v��������ꂽ�B���Z�N��ɂ́A���ۃ��W�[�����������Ƃ��A���̌`����ێ��ɂ����Ĉ��|�I�ȗ͂����e���������݂�����ۃ��W�[�������肷��Ǝ咣����e������_��A������̍��X�̋��͂ňێ����邱�Ƃ�������������_���咣���ꂽ[15]�B
���ł��M���s��[��Z�Z��][16]�́A�ˑR�Ƃ��č��Ƃ��D�z�I�Ȓn�ʂ��߂Ă�����̂́C���݂͎s��ƍ��ƁA�����Њ�ƁA���ۋ@�֓��̍s��̂̑��ݍ�p���A�O���[�o���Ȑ����o�ϊW���`�����Ă���Ƃ��A����珔�s��̂��A���̐����I�E�o�ϓI���v���ɑ剻���悤�Ƃ��āA���یo�ςɉe����^����ƌ���B
�ނɂ��C���S�ۏ�E���ې����V�X�e���́A���یo�ς��@�\����{���I�Șg�g�݂����̂ŁA���Ƃ̎�v�S���ł���B�o�ϖ��Ɋւ��ẮA���Ƃ���Ȉӎv������s���C���̍s��̂͂��̒��ŋ@�\����B���������v�₻���Nj����鐭��́A�x�z�I�Ȑ����G���[�g�A���͒c�̂Ȃǂɂ���`�Â�����̂ł���B
���E�o�ς��ǂ̂悤�ɋ@�\����������邩�A���Ȃ킿���ۓI�ȃ��[����x�Ȃǂ̍��ۃ��W�[���̑n�o�Ə�����ɂ��ẮA���͂Ȏw���͂ƃK�o�i���X�\�����K�v�ɂȂ�B���ۓI�Ɏ��R�Ȍo�ς̑n���ƊǗ��ɂ́A�w���͂�����e�����Ƃ������͓��������𑩂˂�w�����Ƃ��K�v�ł���B���̂悤�ȍ��Ƃ́A�����Ɠ������̗��v�̂��߁A�J�����ꂽ�f�ՃV�X�e���A���肵�����ےʉ݃V�X�e�����܂ލ��ی����������B����ɂ͎��R�Ȑ��E�o�ςւ̊S�������C���̖ړI�̂��߂ɐ����I�C�o�ϓI�������g����z�������͂ƈӎv��K�v�Ƃ���B�����Ă�����x���鍑���I�ȃR���Z���T�X���d�v�ł���Ǝw�E����[17]�B�����Ă��̖�������A���̖������č����ʂ��Ă����̂ł���B
�i�Q�j�p�b�N�X�E�R���\���e�B�A���p�b�N�X�E�A�����J�[�i�U��
��㎵�ܔN�Ƀ����u�C�G�Ŏ�v��i����]���W�܂�A��ꎟ�Ζ���@��̌o�ϐ�������c���Ĉȗ��C���N��v����]�́A���ې����o�ϖ������c�����Ƃ��Ăf�V�T�~�b�g���蒅�����B���̎����́A�u���g���E�b�Y�̐��̕���Ɍ�����悤�ɐ�㐢�E�o�ς̐������x�������ے���������A�f�Վ��x�̐Ԏ����A�h����@�A�x�g�i�����̍����ȂǂŁA�č��̐��E�����ێ��R�X�g���S�\�͂Ɍ��E�������n�߂��B�܂����\�����f�^���g�̗l����悵�C��v���̑����ԋ��c�����߂��鎞���ł��������B���Z�N�㏉��������N�ɂ킽�鋤�a�}�������Ńp�b�N�X��A�����J�[�i�̕��������݂�ꂽ���C�R�g�\�Z�ō����E�o��Ԏ����������Đ��������C�N�����g�������͑����ԋ����Ǘ��^�̍��ې����o�ω^�c���u������������Ȃ������B
����[���㎵]�́A�|�X�g�e���V�X�e���́C���ې����o�ς̊e����ōł����S�I�Ȗ�����ƐӔC�����X���R���\�[�V�A���^�̋����Ǘ��̐���g�݁A�����ړI�Ɨ��Q�̒������J��Ԃ��Ȃ���A���̕���̒����̌`���Ɖ^�c�ɓ�����V�X�e���ƌ���B�e�̈�̃R���\�[�V�A���^�̐��̏d�w�I�ȑ̌n�ō��ے������ێ������Ƃ����\�������A��\���Ɍ����邪�A�����I�ɂ̓J�^�X�g���t�B������ł���\���������Ǝ咣����[18]�B
�@�������㥈�ꎖ����̕č��̒P�Ǝ�`�I�ȍs���́A�Ăуp�b�N�X��A�����J�[�i�����u���������������B�������ɃC���N�푈��̐�凌����x���̔�p�̑����ŁA��v���⍑�A�Ƃ̋����H���ɋO���C����]�V��������Ă���悤�Ɍ����邪�C���|�I�ȌR���́C�L��ȍ����s���������ꂽ���Z�s��A���͂ȏ��Z�p�Ȃǂ�ɐV�����`�Ԃ̒鍑���`��������Ƃ����������炠��B����[��Z�Z��]�́A�L��Ȓn����x�z���邽�߂ɖc��Ȏ�����Q����ÓT�I�Ȓ鍑�ƈقȂ�C���̋Ɍ��I�Ȕ�����̒鍑�́A�������錠�͂��Ȃ��̂ŁC���ډ�����Ȃ��Ă��e�����鍑�̌���ɏ]�����Ƃ����҂ł��A�o�ό������悭�R�X�g���S�ʼn���댯�͏��Ȃ��Ƃ���[19]�B�p�ݐ푈���̊e���ւ̐��S�̗v�����A�C���N�푈��̍��A�����e�F����O���C�����A�K�v�Ƃ�����ۋ��͂𗘗p���āA�鍑�̈ێ���}�낤�Ƃ������������Ȍv�Z�Ɋ�Ƃ��l������B
�č��͋��Y��`�̋��Ђ֑R���邽�߂ɁA�ČR�����j�I���\�͂�c���������C���������������h�q�̐��Ɏ�荞�݁A�⊮��͂�S����������j�ł������B���̌㐼������{�̌o�ϗ͌���ɂƂ��Ȃ��A�h�q��p��ΊO�����̕��S�̌���������߂��B�ӔC���S(burden-sharing)�v���̖{���́A�e�����ł���č����A�����̌o�ϓI�n�ʂ̑��ΓI�ቺ�œ��h����p�b�N�X��A�����J�[�i���ێ����C�g�傷��ׂɁC�����ɕ��S��]�ł���Ƃ���ɂ���B�������̓p�b�N�X�E�R���\���e�B�X�ł��邪�A���ۂɂ̓p�b�N�X�E�A�����J�[�i�U�ł���ƁA���[����Z]�͎w�E����[20]�B
�č����e���ɐӔC���S�����߂闝�_�I�����Ƃ��āA���ی��������_������[21]�B����ɂ��Ǝ��R�f�Ց̐��A���ۈ��S�ۏ�Ȃǂ����ی������ƋK�肵�C�t���[���C�_�[�����݂���A�R�X�g���S�̐���ōœK�������s�\�ɂȂ�Ƃ���B�e��������č��͎����̏��։v���v���X�ł������A��ʉ݁A���ےʉ݃V�X�e���A���S�ۏ�̐��Ȃǂ̌��������������A���ׂĂ̍������b��������B���։v���}�C�i�X�ƂȂ�A���ی����������̃C���Z���e�B�u�������C���ێЉ�͍����△�����������₷���Ȃ�B�����ŃR�X�g���S�ɔ�ׂĉ��b���Ă�����i�����A�Ƃ��ɓ��{�ɉ����̕��S�����߂�Ƃ��������ƂȂ�B
���������ی��������_�ɂ͔ᔻ������B�����Ԃ̈��S�ۏ�V�X�e���́A�r���s�\�̓������������A���̢�N���u�ࣂł���A�܂����ےʉ݃V�X�e����č��̐Ԏ��t�@�C�i���X�ɗ��p����ꍇ�C����͌�������莄�I���ɋ߂��Ȃ�B���̂悤�ɃC�f�I���M�[�F�̋������ی��������_��p���āA�č��͈��S�ۏ�Ɗ�ʉ݂Ƃ��������j�I�������𒆐S�ɒS�����C�����ɑ�������ς˂�`�̕��Ƃ�i�߂Ă����Ƃ�����B�č��̊S�̓p�b�N�X��R���\���e�B�X�̎������́A���v�D��̃p�b�N�X�E�A�����J�[�i�U�ł��낤�Ƃ̍��̌����ɔ[����������B
��\��@�ב���̐����o�ϊw
�@�ǂ̈ב֑��ꐧ�x���̗p���邩�A�Œ肳�ꂽ����̕ύX�C�ϓ����ꐧ�ɂ����鑊�ꐅ���̊Ǘ��Ȃǂ��܂ވב���Ƃ��̉����̒ʉ݊O���́A�ΊO�W�͂������A�����̗l�X�ȍs��̂̍����������Q�Ɋւ��̂ŁC�ɂ߂Ę_���I�Ȗ��ł���B����Ɋւ�鐭���o�ϊw�I���͂̎�����������Č��悤�B
�i��j�Љ�I���͊W���p���[�E�G���[�g�_
�q��[�����]�͏��w���̃T�[�x�C���s�Ȃ�����ŁA���ےʉݐ������͂Ɋւ��ėL���ƍl���邱�̘g�g�݂���Ă���[22]�B
�i�P�j���ےʉݐ���ɂ�����錈�襎��s�ߒ��̕��͕��@�ɂ��čl�����ׂ����ӓ_�͎��̒ʂ�B
�@ ���v�W�c�_�⑽����`�̗���ɂ����A���Ƃ̐ϋɓI�Ȗ�������ۂ���B
�A ���Ƃ̐���́A�Љ�W�c��K���Ȃǂ̌o�ϓI�C��o�ϓI�v������ǂ̒��x���R�ł��肤�邩�B
�B ����ߒ��ł̌l��W�c�̈ӎ��I�C�F�m�I�ȗv���B
�C ���Ƃ�Љ�̏����x�A���[���A�K�͂Ȃǂ̐���ߒ���W�J�ߒ�������Â�����x�B
�D �����������یo�ϊW�̐i�W��]�����A���یo�ϊW�̗v���������v���ɋy�ڂ��e���ƁC���̋t�̉e���̕]���B
�i�Q�j�Љ�I���͊W���p���[�E�G���[�g�_�I�A�v���[�`�̍��q�B
�@ ����̗��Q�ӎ��Ɛ����ڕW�������������闘�v�W�c���u�Љ�I���́v�ƋK��B
�A ���̂悤�ȎЉ�I���͂�A���Ƌ@�\�����ŋ�����������I�͂����c��C�����ȁC������s�Ȃǂ��p���[�E�G���[�g�ƋK��B�}�X�R�~������ɏ�����B
�B �����̑Η��ƘA�q�W�̂��Ƃł����Ȃ�Љ�I���͂�w�i�Ƃ����p���[�E�G���[�g���w�Q���j�[�����邩�ŁC���Ƃ̐������ĉߒ��Ǝ��s�ߒ��̊�{�I�Ȑ��K�肳���B
�C ���Ƃƌo�ς̕Ґ��C�o�ϓI������I�����x�A�����I���邢�͈Öق̃��[���A�K�͂́A�����́A�p���[��G���[�g�̐����ڕW�ƍs���ɉe�����y�ڂ�����B
�D �w���Ҍl�C�w���w�A�Љ�I�W�c�̐S���I��F�m�I�������Љ�I�����͂̐����I�I�D��ӎv����ɉe�����y�ڂ��B
���̂悤�Ȋϓ_����C�ނ͍��ےʉݐ���Ǝ��s�̕��͂ɂ����āA�Y�ƊE�A���Z�E�A�c���{�@�\�̃p���[�E�G���[�g�A�}�X�R�~�̓����ɋ����S�������A�j�N�\���E�V���b�N�Ɏ�����Ēʉ݊O�����r�E���͂����B
(��)�ב֑���̐����o�ϊw
�@�ב֑��ꂪ�o�ύs��̂ɋy�ڂ��e���ɏœ_���i�������̘͂g�g�ݒ����݂����̂ɁA�t���[�f���̘_��������B���_�̐����ɖ𗧂̂ŗv��[23]�B
�ނ͎����ʉ݂̑ΊO���l���e���̐������ǎҁA�A�i���X�g�C�����ƂɂƂ�܂��܂��傫�ȊS���ƂȂ�A�܂������o�ϓI�_���̎��ƂȂ��Ă���Ƃ��A��̖���_����B
�i�P�j�ב֑���̐����I�d�v���̕ω��B�o��E���{����̎��R���ɂƂ��Ȃ��A�ב֑���ϓ������z�ɉe�������߂�̂ŁA�ב���̐������͔����������B
�i�Q�j�ב֑��ꐧ�x�̑I�D�ɂ��āA�����I�ȕ��f�����݂���B�Љ�I�O���[�v���قȂ�C�Œ葊�ꂩ�ϓ����ꂩ�C�ߑ�]�����ꂽ���ꂩ�ߏ��]�����ꂽ���ꂩ�ɂ��Ă̑I�D���قȂ�B
�@���Z����ƈב֑���
�ב֑���̈��萫�A���ێ��{�ړ��A���Z����̓Ɨ����̊Ԃ̃g���[�h�I�t�ŁA�ב֑���͋��Z����Ƒ��݂ɐ������ƂƂ��ɁA�����̏�ʂł��Љ�o�ϓI�W�c�̊����ɉe������B
�A�ב֑���ϓ������Ή��i�ɗ^����e��
���Z�I�ɊJ�����ꂽ�o�ςł́A���Z����͈ב֑���ɉe�����C�f�ՍृT�[�r�X���f�ՍृT�[�r�X�̑��Ή��i��ω�������B���Ƃ����Z�ɘa�͈ב֑�������������A�����Y�f�Ս����i���O���Y�f�Ս��ɔ�������A����ɔ�f�ՍृT�[�r�X���Y�҂ɂ��I�ȉe���������炷�B���Ή��i���ʂ́A����̗��Q�W�҂ɂ͑����I�Œ������̂ŁA����W�c���琭���I���͂����܂邾�낤�B
�B�ב֑��ꐧ�ւ̈قȂ����I�D
���܂��܂Ȍo�ϓI�s��̂́A�ב֑���̈���ƍ����̋��Z��ɉe�����y�ڂ����Z����̊Ԃ̃g���[�h�E�I�t�ɂ����āA�قȂ������Q�W�����B
��f�Ս����Y�҂ȂǍ����̌i���Ɉˑ�����o�ύs��̂́A���Z����̓Ɨ��������߂�̂ŁA�ϓ��ב֑��ꂪ�I�D�����B
��ʂɍ��ۖf�ՂⓊ���ɏ]�����Ă���l�X�́A���̌o�ϓI�p�t�H�[�}���X�ɑ傫�ȉe���������炷�ב֑���̗\���\�����d�����A�Œ�ב֑��ꐧ���D�ށB
���ۓ����Ƃ��A�ב֑��ꐅ���������̕ω��Ɍ��O�������������Ȃ��B
�O���[�o���ɐ��Y�����l�����Ă����Ƃ́A�ב֑���̐����ɂ͕q���łȂ����A�����v����`�������ŁC�s����Ȉב֑���͖��ƂȂ낤�B
�C �ב֑��ꐅ��
�f�Ս��̐��Y�҂́A���ΓI�Ɍ������������ʉ݂��D�ނ̂ɂ������āC�A���ƎҁA����҂͑������������ʉ݂��D�ށB���ۓ����Ƃ͎��Y���i�Ǝ����̗����ɊS�����B�ב֑���̑����́A�����ʉ��ĂŊO���Ď��Y���������邪�A�����̗���̉��l�����炷�B
�D�ב���̐�����
���E�����Z��f�ՓI�ɓ��������ɂ�A�ב֑���ɂ��Ă̐����I�_�������܂�B�ב֑���̐����Ƃ��̕ϓ��͈͔̔@���ɂ��A���X�̌o�ύs��̂̊Ԃɕ��z��̑Η��ނ悤�ɂȂ�C�}�N���o�ϐ���`���́A��萭���������B
�ב���ɂ��Ă��A�o�ύs��̊Ԃɐ����I�ȑΗ������܂�B�ב֖�肪�����������A�����I�������ݓI�����̐V�����g���������܂��B����𗝉����邱�Ƃ́A���ې����o�ϕ��͂̑����ł���B
�i�O�j�{�e�̖��ӎ��ƈˋ����闝�_�I�g�g��
����܂ł̓��{�́A�p�b�N�X�E�A�����J�[�i�̎�v�҂̗�������Ă����B���̊S�́A�ŏI�I�ɂ͋t�炦�Ȃ��č����A�����ɂ��܂����p���邩�ɏd�_������A�č��������̐헪�𐋍s����̂ɍv������Q�ƂȂ�ʌ���C�����ƃA�W�A�̖h�q�̍ԂƂ��Ă̓��{�̗���d���Ă����B���������Ă̌o�ϗ͊i�����k������ɂ�āC�t���[���C�_�[�̔��𗁂тĐӔC���S�𔗂��A�܂��\�����v�����߂����ʂ����債�Ă������A���C�╴�������ĊW������I�Ɉ��������钼�O�̂��肬��̐��܂ŁA�e����̊��������͓��{�̢���v�[24]����邽�߂ɒ�R���A���ǂ͐����I���f�œ��ĊW�̔j�ǂ��������Ƃ����`���J��Ԃ��Ă����Ǝv����B
�����Ĉב���́A���̐摗���}���i�Ƃ��ď\���Ȕ�p���ʂ̕��͂��Ȃ��C�܂������I�ȍ��ې����o�ϓI�헪�̒��ł̈ʒu�t�����Ȃ��܂܂ɑ��p����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪����B���̋^����𖾂��邽�߂ɁA�ϓ����鍑�ۓI�g�g�݂̒��ŁC���܂��܂ȍ������s��̂��ǂ̂悤�ȍs�����Ƃ��Ă����̂��A���̓��@�͉����A���ꂪ���ۊW�ɂǂ̂悤�ɉe�������̂��ɂ��āA�����I�Ȍo�ϊw�I���͂Ƃ͈قȂ����ϓ_����̉��߂�]�������݂邱�ƂƂ������B���̂��߂Ɉˋ��������_�I�g�g�݂��ȉ��ɗ��q����B
�i�P�j�v�����V�p���E�G�[�W���g���_[25]
�@�ב���͑呠�Ȃ̍������A���ۋ��Z�ǒ��𒆐S�ɍ���A���s����Ă���[26]�B�ނ�͐����}�o�g�̐����Ƃł������(���呠)��b�̎w�����ɂ��邪�A�����Ȃ̒��ł���含�̍�������ł���A�܂������@�����Ɛv������v���邽�߁A���������ڊ֗^���邱�Ƃ�����ł���C�ނ�̍ٗʂɔC�����͈͂͑��̍s�������ɂ���ׂėy���ɑ傫���A�܂����Ȃ̑�����ɔ�ׂēƗ����������悤�Ɍ�����B
�@�c�@���t���ɂ����Đ������}���ǂ̒��x�����̍ٗʂɈς˂邩�́A���G�Ȗ��ł��邪�C����͐�含��������̊ϓ_����A�������s�������ɈϔC����������Ȃ��B���{�ł͐�O����̓`�����}�x�z�������Ɍp���������Ƃ�����A���ɈϔC�̕����傫���A�����͗D�ʂɂ���Ƃ����̂�����̌����ł������B
�@���������������[��Z�Z��]�́A���܁Z�N�̎�v�Ȑ���͊����ł͂Ȃ��A�����Ƃ̃��[�_�[�V�b�v�Ő����ߒ������߂��Ă����Ǝ咣����B���Ĉ��ۑ̐��̈ێ��C����ԊҁC�����{���A����ŁA�����A���������Ȃǂ����̎咣�𗠕t����B�|��[����O]���A�����͓��a���I�s�����Ƃ�X��������A�r�W�l�X����[�_�[�����́A���������̗��ꂪ��������鋰�ꂪ����Ƃ��������݂̂ŁA���Ǐd�v�ȃ}�N���o�ω^�c�̍ŏI����́C���̑�����b�̃��[�_�[�V�b�v�A����ёI���ł��߂��ꂽ���_�Ɋ�Ă����Ƃ̍����ׂ̉����i���{�Ő��}���_�j�������C���ۓI�V���b�N�ɂ��z�������A������S������h���Ԃ̐���i�����o�ϕϓ��̗v���ƂȂ��Ă���ƌ��_�Â��Ă���[27]�B���������ċɂ߂ďd�v�Ȑ���̌���⏳�F�͐������}�̐����ƏW�c���s�Ȃ��C����Ɋ�������Ɩ������s����v�����V�p����G�[�W�F���g�W�������I�ɐ������Ă���悤�Ɍ���������B
�@�����}�ƍ����Ȃ̈ϔC�W�́A�@���ɂ��s���@�ւƌ������ɗ^�����錠������߂��Ă��邪�A���ۂɂ͂���������̒����I�W�ƂȂ��Ă���B�`���I�ȗ��_�ł́C���̔�Ώ̐��̑��݂�O��ɁA�s�\���ȏ����g���āA�m���Ƀv�����V�p���̂��߂ɓ����Ƃ͌���ʃG�[�W�F���g�������ɃR���g���[�����邩�����̏œ_�ł���B���Ɍ����z���͐����I����v���Z�X���l�����ŏd�v�ł���B���x�゠�邢�͖@�I�Ɍ��茠�����^�����Ă����̂ł��A�����I�Ȍ��������Ƃ͌���Ȃ����Ƃ́A���呍��̗�ł����炩�ł���B�����I�����̏��݂��ӎv����̖����l�����ŏd�v�ł��邪�A��{�I�ɂ͗D�ꂽ����m��������̂Ɏ����I�������t�^�����X��������A���ꂪ�v�����V�p���̗��v�ɂ��Ȃ��B�����}�ƍ����Ȃ̊W���A�����ł������Ƃ����悤�B
�@�v�����V�p�����\���ȏ������ꍇ�C�G�[�W�F���g�̏���m���ɗ��炸�C�����Ō��肷��悢���C����̓G�[�W�F���g�̒m������~�ς̃C���Z���e�B�u��D���Ă��܂��B�����Ŋ����ăG�[�W�F���g�Ɍ��茠�����������邱�Ƃ�����B�ב���̕���ł��A��含�̍����������ƌ�����������A���ۋ��Z�ǂɎ����I���茠�����ς˂���[28]�B�B���ꂪ�܂����~�ς̃C���Z���e�B�u�������߂邱�ƂɂȂ�B�������G�[�W�F���g�͎����̗��v���ő�ɂ��錈������A�v�����V�p���ɕs���v�������炷�\��������B�G�[�W�F���g�ł���������A���ۋ��Z�ǂ͂ǂ̂悤�ȃC���Z���e�B�u�ōs�����A������v�����V�p���̐����}�A�����Ă��̃v�����V�p���ł��鍑���͂ǂ̂悤�ɊĎ����]�����ׂ��������ƂȂ낤�B
�i�Q�j�����I�A�N�^�[���_�@
�ב����ۊW�Ɛ[���ւ��ƂƂ��ɍ����̏��s��̂ɕ��z��̃C���p�N�g��^���邱�Ƃ���A�v�����V�p���ł��鐭���}�ƃG�[�W�F���g�̒ʉݓ��ǂ̐���`���Ɋւ��s���͂�����@�ɂ��Ă�蓥�ݍ��������K�v�ł���B���̓_�ɂ��ẮA���ࢍ����I�A�N�^�[�i�s��́j�A�v���[�`�irational-actor- approach�j����Q�l�ɂȂ�[29]�B���̃A�v���[�`���ב���Ɋւ��Ẵv�����V�p���ł��鐭���}�A�G�[�W�F���g�ł���ʉݓ��ǂƂ������I�s��́A�����Ă��̐���̉e������Љ�A�N�^�[�܂��͎��I�s��́i��Ƃ��̑����v�W�c�A���O�j���ǂ̂悤�ɍs�����邩�A�����̐헪�I���ݍ�p���ǂ̂悤�ɑ����邩�Ƃ������ڋ߂����|����ƂȂ肤�邩���������Č���B
�@���̃A�v���[�`�ł́A���s��͎̂�Ƃ��đg�D�����̒Nj���ړI�ɁA���荇���I�ɍs������Ƃ���B���Ȃ킿���ꂪ���Љ�W�̂�����ɂ��Ă̕s���S�Ŏ�ϓI�ȃ��f���Ɋ�C�헪�I�ɑ��ݍ�p���邪�A���̌��ʐ����I�ȗ͂ɉ����ēK���Ȗ�����`�ň��̋ύt����������B
���s��̊Ԃň���I�ɋ��L���邱�ƂɂȂ�Љ�I�ȃQ�[���̃��[���Ɋւ��鋤�ʔF���A���L���ꂽ�\�z������x��ƂȂ�B�����Ő��x�̕ω��́A�s��̊Ԃ̋��ʔF����h�邪���V���b�N�A����ɑ���e�s��̂̐헪�I�Ή��ɂ���Ă����炳���B���̋}���ȕω��ɑ��āA�������v�A�Đ��C�T���N�R�X�g�Ȃǂ̗��R�ŔS������������������o�ϐ��x���K���ɒx���ꍇ�C���x�ω��Ɋւ��ė��Q���قɂ���s��̊Ԃ�g�D���W�c���x�z�����߂��葈���A�N���e�B�J���E�}�X�̍s��̂��u���̒��̎d�g�݁v�ւ̌�����ω�������ƁA�V�������x�̒a���ɂȂ���B
�@���I�s��̂ł��銯���́A�����Ȓ��̑g�D�I���v����ɍv�����邱�Ƃ��A���̑g�D�ł̎嗬����ނ��ƂɂȂ��Ă���A�g�D�������Ȃ킿�����i���ׂĂ̍s��̂����L����\�z�̃��x���ŁA���̏Ȓ��������]������j�̍ő剻��}��C���Z���e�B�u�������B����͕K�������K�������̍ő剻�Ƃ͈�v���Ȃ��B���������߂邱�Ƃő��̍s��̂ɉe���͂��s�g���邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�g�D�������m�ۂ��邱�ƂŁA�Ȓ��͋ƊE�������s���ւ̋��́A�V�����̃|�X�g�̗��v��B�܂���ʍ����̎x���邱�ƂŎЉ�I���������߁C�g�D�������m���ɂł���B
�@���I�s��̂ł����ʍ����͑g�D������Ă͂��Ȃ����A�I�����̑��̒��ڍs���Ő��}�։e���������炷���C�u���v�v�̗i��҂Ƃ��Ċ������@�\���邽�߂̎x����ՂƂȂ�B�g�D�����ꂽ���I�s��̂ł�����E��ʊ�ƂɂƂ��Ĉ�ʍ����̓G�s���͒v���I���ʂނ��߁C���̍s��̂͂��̎x�����ɑ剻����헪���Ƃ炴��Ȃ��B��������ʍ����̗���\�͂◘�p�\�ȏ��̐����邽�߁A������E���Ȃǂ̌����̍s��̂́A����̗��v��ڕW�ɉ����悤�Ɂu���v�v�̒�`�𑀍삷��\��������B
�@���{�ł͐�����E���̍s��̊ԂɈ��肵���������������}�ƍs����ʂ��Ċe�̈�ōs�Ȃ��颊�����������`(bureaupluralism)��Ȃ�����d��ꂽ������`������݂��A���x�����ɍv�����}�N����V���b�N�ւ̏_��ȑΉ����\�ɂ��Ă���[30]�B�����ł͌�������͌��I�s���(�����Ƃ⊯��)�Ƌ��͂Ȏ��I�s���(���ƁA�ƊE�c�̂Ȃ�)�Ƃ̑��ݍ�p�f���邪�A���O�̐����o�ϊW�̕ω��ŁA���胁�J�j�Y���ɂ��ω�����������B�l�@�Ώۂ̈ב���A���Ɉב։������͒ʏ�����ȂǂƈقȂ�B����v����@������v���邵�A���Ɍ��I�ȓ]����K�v�Ƃ���ʂ�����C���������Ďd��ꂽ������`�̉��ł̃v�����V�p����G�[�W�F���g�Ƃ����C���T�C�_�[�ɂ�鐭��ߒ����I�邱�Ƃ��l������B�{�e�ł́A����������v�̗i��ң�Ƃ��Ă̖����̍ő剻��ʂ��đg�D������}��Ƃ��������ŁA�ʉݓ��ǂ̍s�����ǂ̒��x�����\���ɂ��Ă������ۑ�Ƃ������B
�i�R�j�摗�茻��[31]
�@�傫�ȍٗʌ������ς˂�ꂽ�ʉݓ��ǂ��A�Ƃ��ɂ͉B���ɁA�Ƃ��ɂ͌��R�Ƌ��z�Ȏ����ňב֎s�������s�Ȃ��ړI�́A�}���Ȉב֑���̕ϓ��̗}���Ƃ������Ƃł��邪�A�����̏ꍇ�C�i�C��Ƃ��Ă̗A�o�Y�Ƃ̋����͈ێ��A�����ʂ��Ă̌o�ϐ����̈ێ��ɂ��̖ړI���������ƌ����Ă���B
�@�����A��i�e���̓u���g���E�b�Y�̐��ɓK�����鐭���o�ϑ̐����\�z�������A���Z�N��ɂȂ�Ɨl�X�Ȑ�����o�ϊ�@���������A���{�͍����̔�����I�ł͂��邪�����I�ɋ��͂ȕ�����������Ȃ���Q�i�I���ۉ����g�̍��ۋ����őΉ������B����ɑ��đ��̐�i���́A���̐��̊�Ղ��\���ω��𐋂�����Ƃ̔F���̉��ŁC����ɓK������K�����v��i�߂�Ȃǂ̎��Ȋv�V��Nj��������ʁA�މ�̌��u���g�債�đΊO���C�ݏo�����B���{�͊O��������ɉ������Ȃ���A���{�I�ȉ��v��摗�肵�Ă����̂ł���B
�@�摗�茻�ۂ́A�@�����F��������f�̒x��A�A���������◘�Q�����̒x��A�B����̈Ӑ}�����o�ό��ʂނ܂ł̒x��ȂǂɋN������B�摗�茻�ۂ̕��Q�����Ȃ�����ɂ́A�i�@�j�o�ό��ۂ̎��Ԃ�K���v���ɔF�����A���{�I���v�ƌ���ێ��̗��Q�����m�ɕ]�����邱�ƁA�i�A�j���̐M�������m�ۂ��邱�ƁA�i�B�j���v�c�̊Ԃ̗��Q�������~���ɂ��C���S�z�������������āA���̋A�����ɂ��邱�Ƃ��̗v�ł��邪�A���̂��߂ɂ͐����I�ӎv����V�X�e�����̂̉��v���K�v�ł���C�����̃R�X�g�������Ă����{�I���v�����{���A���Ă�摗�肵�Ȃ������I�w�������K�v�ł���B
�@�������Ȃ���A����܂ł͑傫�ȕϓ��Ɍ������č����̐��̌���������v��K�v�ƂȂ��Ă��A�����}�⑼�̊����g�D�����o�ύs��̊Ԃ̗��Q�����Ɏ�Ԃǂ�A�ΊO�W��o�Ϗ������I�Ɉ������邨���ꂪ���݉����Đ����}�}���f�𔗂���܂ŁA���������摗�肳��邱�Ƃ������ł������B���̊ԁA�������~�����И_�Ɍ}�����邱�ƂŖ������ێ��ł���ʉݓ��ǂ́A�傫�ȍٗʂƎ���I�ȕ]���̌��@�Ɏ���Ȃ���C�ב֎s�����Ŏ��ԉ҂�������P�[�X�����Ȃ��Ȃ������Ƒz�������B���̓_���������K�v�����낤�B
�i�S�j�ב։���s���̗ތ^���Ɋւ��鎎�_
�@�ȏ�ɊT�ς��������o�ϊw�̗l�X�Ȓm�������p���ċ�̓I�Ȉב։��������ώ@��������[�ߕ]�����s�Ȃ��ɂ�����A�ȉ��̔@������s����ތ^�����Č������B
�@ �W���^����F���@�I�v�f�ɂ��ב֑��ꂪ�������������͈�������ɕϓ����A�o�σt�@���_�����^���Y�f���Ȃ�����̓����ɑΉ�����ꍇ�̉���B
�A �ً}���^����F���u����V�X�e�~�b�N����X�N������s�\�ɂȂ邩�A�ʉ݂̎��~�߂Ȃ������������ȂNJ�@�I�ւ̑Ή��Ƃ��Ẳ���B
�B �A�o�u���^����F�����ʉ݂��Ӑ}�I�Ɉ����ۂ��C�A�o�g��A�A���}���A�O�ݒ~�ς�_������B
�C ���摗��^����F���ۊ��ω��ւ̓K���ɕK�v�ȍ������x��K���̉��v�Ɏ��Ԃ������邩�A��������摗�肷��ԁA�ב֑���ւ����鈳�֑͂Ή����邽�߂ɍs�Ȃ�����B
�D �Εċ����^����F��i�����֔e���ێ��R�X�g���S�����߂�č��ւ̋��͂Ƃ��Ẳ���B
�ތ^���̖ړI�́C�ב։���s�����ώ@�����ʂ�]������ꍇ�C����Ɋ֘A���Ȃ��琳���I�Ȍo�ϊw�ł͒ʏ���グ���Ȃ����A����`������{�ɉe�����y�ڂ����ƌ����鏔�v�f��E�o�E�������D��t�����s�Ȃ����Ƃɖ𗧂Ǝv���邩��ł���B
���Ȃ킿����܂ł̓��O�̌o�ϊ��̕ω��A����ɑ�������s��̂̔F���ƑΉ��C���̒��łǂ̍s��̂��哱���ĕω��ɑΉ����鐭��̌`���ɉe����^�������C����̓^�C�~���O�悭���{���ꂽ�̂��A����ɂ�藘�v����s��̂ƕs���v��ւ�s��̂͒N���C�܂����Q�Η��̒����Ɏ�Ԃǂ��Ċ�{�I�Ȗ��������摗�肳��A�����߂ʼn�����o�������̂ł͂Ȃ��������Ȃǂ��l�����ł̎茜��ƂȂ낤�B��������̗ތ^�őS���������ł��Ȃ��ꍇ�������Ǝv���邪�C�������̑g�����ōl����ɂ��Ă��A����s���̓����̔c���ɖ𗧂̂ł͂Ȃ��낤���B
�@
�O�@�j�N�\����V���b�N����Ζ���@���O�܂ł̈ב���
�@�u���g���E�b�Y�̐�����O�ォ��A���O�N�̕ϓ��ב֑��ꐧ�ڍs�Ɏ���Ԃ̎�ȉ���̎�����������āC�����o�ϊw�I���n����̕]�������݁A���̒�����ב���̖ړI��ʉݓ��ǂ̉���s���ɂ��Ăǂ̂悤�ȉ��߂��\���ɂ��čl����B
�u���g���E�b�Y�̐��́A���Z�Z�N�㖖�����瓮�h���͂��߁A���Z�N�㏉���ɂ́A�܂��Ɍ��������}�����B����N�����̃j�N�\����V���b�N�ŁA�����l�����I���������h�l�e�̐����̒����\�ȌŒ葊�ꐧ�̋@�\����~���C��v���́A�ϓ����ꐧ�ֈڍs�C���̌㎵��N���̃X�~�\�j�A���̐��ƌĂ��Œ葊�ꐧ�ɕ��A�����B����ɂ��~�̑h������͈�Z���������グ���āC��h���O�Z���~�ƂȂ����B
���������̒ʉݒ����ɂ�������炸�C��v���Ԃ̍��ێ��x�s�ύt�ƒʉݓ��@�͉��������A���Ɏ�v���ʉ݂͎��O�N����O���ɂ����čĂѕϓ����ꐧ�Ɉڍs���A���݂Ɏ������B�܂��X�~�\�j�A���ł̒����ɂ�������炸�C�{�M�f�Վ��x�A�o����x�̍����͑啝�ȍ����������C�������邩�Ɍ������B�i�J�[�u���ʂ̔����Ƃ������́A�����s���Ƃ̌������x�z�I�ł������B���̊Ԃ̈ב���̐��ڂ�Օt����[32]�B
�O�\��@�j�N�\����V���b�N����X�~�\�j�A�����ӂ܂�
�@���{�Ɛ��Ƃ̖f�ե�o����x�������ˏo���Ă������߁A���ʉ݂̐�グ���ϓ����ꐧ�ڍs�����ےʉݖ��̏œ_�ƂȂ��Ă����B���������{�����ł́A�ɂ߂ċ����~�����И_�Ȃ����~�����_�����݂��Ă���[33]�B�ꕔ�̌o�ϊw��[34]��ʉݓ��ǂ̎����҃��x��[35]�ł́A�~�̐�グ�C�������͕ϓ����ꐧ�ւ̈ڍs���咣������������������A���{��]����ʉݓ��ǂ́A�����I�Ȏv�f������A�ב֊Ǘ������ɂ��Œ葊�ꌘ���̕��j�𑱂����B
�@����N������ܓ��̃j�N�\��������C����܂ŌŒ葊�ꐧ���ێ����Ă������X�͈ב֎s�����A���̌�ϓ����ꐧ�Ɉڍs�����B���{�ł͈ב֕ϓ����������b��I�ɒ�~�����������܂ŁA��������ɂ킽��s����J�����܂܁A��h�����O�Z�Z�~�̈ב֑�����ێ����������B
�Ȃ��ב֎s����J���������̂ł��낤���B������Z���̑呠�ȁC����ً̋}������c�ł́A�ב֎s����̉ۂ��_����ꂽ�B���B�����ɂȂ���Ďs��������̐��ڂ𒍎����ׂ����Ƃ���咣�����������C���ۋ��Z�ǂ𒆐S�ɖ{�M�̓��ꐫ�������Ƃ��Ĕ��Θ_���咣�A�����������x������[36]�B���ǐ��c�����ْ̍f���o�āA�����̊t�c�Ŏs����J�����܂܌��s�ב֑���ŌŒ�ב����ێ�������j���m�F���ꂽ�B
���̊ԁA�ʉݓ��ǂ͔�����Z����������̎l���Ԃœ�h���A�b��I�ϓ����ꐧ�ڍs�̓��܂ł̈����ԂɎO��`�l�Z���h���Ƃ����鋐�z�̃h������������s����[37]�B���Z��N�A���Z�N���̊O�ݏ����z�́A���ꂼ���O�܉��h���Ǝl�l���h���ł���A���̉���K�͂̑傫�����f����B���̌��ʁA�O�ݏ����z�́C����N�������ɂ͈��܉��h���C�N���ɂ͈�ܓh���ɂȂ����B�h������̒��S�́C���ЁA���[�J�[�Ȃǂ̗A�o�O���̗����A��̊O�݃|�W�V�����̒����ł��邪�A���[�Y�E�A���h�E���b�O�Y�Ȃǂ͓��ǂ̗\�z������K�͂ł�����[38]�B
�@�@���������̑呠�ȏȋc�ŕϓ����ꐧ�ڍs���j�����肵�����A���{����T�Ԑ�Ƃ����B����͗A�o�Y�ƁA��s�̑Ή��Ɏ��ԓI�]�T��^���邽�߂ł�����[39]�
�������ɕϓ����ꐧ�ֈڍs��������C�ʉݓ��ǂ͑�ʂ̃h���������p���������C�Z��������}�����邽�߈ב֊Ǘ��������A�~���}�~�ɓw�߂��B�㌎�����܂ł̊O�ݏ��������z�͓��h���ł������B
�@�b��I�ϓ����ꐧ�ڍs��̑���`���́A������ʉݓ��ǂ̎�Ɉς˂�ꂽ�ŁA���X�̑��ꐅ���͐��c�����̎w�����C��̓I�Ȏs��^�c�ɂ��Ă͑呠�ȂƓ��₪�ٖ��ɘA�����Ƃ�Ȃ���C�f10��c�̐���s���A�������_�̓����A�s��̔��������Ȃ���A�����Ďs�����ƈב֊Ǘ�������ɁA�Ȃ��炩�ȉ~�����ۂ��C�]�܂����h���~����Ɍ����ă\�t�g�E�����f�B���O�����݂��Ƃ���[40]�B
���̌��ʁC�ϓ����ꐧ�ڍs����̔������Ɉꋓ�ɋ�������ܥ�㏸�������ƁA��Z�����܂Ŕ����ꁓ���x�̃y�[�X�łȂ��炩�ɏ㏸�����B��������ꌎ���{���f10�ł̒ʉݒ����̋@�^�̍��܂�Ƌ��Ɏs��͔g���܂݂ƂȂ�C���͂Ȏs�����őΉ������B�㌎�����Ɏ��{�����h����������͎O�Z���h��������K�͂ł������B
�@���̌�����ےʉݏ�͈��肹���A�Œ葊�ꐧ�ւ̕��A�͌����I�ő��p�I�Ȓʉݒ����̉ۂɂ������Ă���A�~�͂��̏œ_�ɂȂ��Ă����B�j�N�\���E�V���b�N��̍����̎��E�ɂ́C��v���Ԃ̒ʉݒ������s���ł���A��A�̍��ۉ�c�ł��ʉݒ����̕��@�ƕ��A���C�_�[�o���h�̗p�̖�肪�_����ꂽ�B�����̕��@�Ƃ��ẮA�����i�̈��グ���܂ނ��ۂ��������ĕč��Ƃ��̑��̍����Η������B��҂͒ʉ݊�@���č��̍��ێ��x�̖����I�Ԏ��������ł���ȏ�C�č��ɂ��w�͂����߂�̂����R�Ƃ����B
�@�č����{���ł��A�j�N�\����V���b�N�ȗ��������o�߂��Ēʉݕs���������Ă���̂́A���E�o�ςɈ��e����^���C���ۋ����Ȃ��Ƃ������O�������܂�A����N��ꌎ���̃��[�}�ŊJ�Â��ꂽ�f10�ŁA�~�̓�Z�����x�̐�グ���܂ޕ��ψ�ꁓ�̎�v���ʉݐ�グ�Ȃǂ������ɗA���ے����Ȃǂ̔p�~��A�h���̈�Z�����̐؉������Ӗ���������i���グ���������ĎQ�����ɏՌ���^����[41]�B����܂ŃR�i���[���������͕č��̍��ێ��x���P��O�Z���h�����\�ɂ����v���ʉ݂̐�グ��v�����A�����i���グ�C�A���ے����p�~�����ۂ��Â��Ă������C���̋��d�p���ɑ��āA�L�b�V���W���[�哝�̓��ʕ⍲���ƃo�[���Y�A�M�������x������c�����o�ς�O����D�܂����Ȃ��ƃj�N�\���哝�̂ɐi���������ʁA�����]�������Ƃ�����[42]�B
���̌�L�b�V���W���[�̃V�i���I�ʂ�ɁC���O�A��l���A�j�N�\���ƃ|���s�h�[���哝�̂��A�]���X�ʼn�k���A�����i��č��͋���g���C�E�I���X���O�܃h������O���h���ֈ��������邩���ɁA�t�����X�̓h���̋������ʗv�����Ȃ����ƂȂǂ����ӂ����B���̌��ʁC�ʉ݂̑��p�I�������\�ƂȂ���[43]�B
�@�ב֎s��ł͒ʉݒ������҂����܂�C��ꌎ���{���珤�Х���[�J�[�̃��[�Y�E�A���h�E���b�O�Y�Ȃǂɂ�銈���ȃh�����肪�Ĕ����A����ɑΉ������v��l�s�̃|�W�V���������h������͈���{�܂łɖ��܉��h���ɒB�����B���ǂ͋��͂ȉ���ʼn~�̏㏸���A��ꌎ�����̎O�~�Z�ܑK���獇�Ӓ��O�̎O��Z�~�Z�Z�K�Ɣ�r�I�ɖ��ɗ}�������̂́C����z�͎O�Z���h��������K�͂ɒB����[44]�B
��ꎵ�A�ꔪ���A�f10�����E����ى�c�����V���g���̃X�~�\�j�A�������قŊJ����C���{����͐��c�����A���X�ؓ���فA���ؑ呠�Ȍږ₪�o�Ȃ����B�ő�̒��ړ_�͉~�̐؏グ���ł������B���������̐�グ���ɂ��Ă̎w���́A���،ږ�ɂ͈�܁��A���c�����ɂ͓�Z���Ƃ�����B���{���́A��j�N�\���V���b�N�シ�łɈ�܁��㏸���A�������s���ɂ��飂Ǝ咣���A�č��̓�Z����グ�v���͖ܘ_�C�ꎵ����グ�v���ɂ����c�����͒�R���A���Lj�Z��������̐�グ�ō��ӂ���[45]�B
�O�\��@�X�~�\�j�A�����ӌ��㎵�O�N�̕ϓ����ꐧ�ڍs�܂�
�~��グ�C�e�퍑�ێ��x������ɂ�������炸�A����N���Έȍ~�A�o����x�����͍Ăъg�債�͂��߁A����N�Z�����̃|���h��@�ȍ~�C�h���~����́A�X�~�\�j�A�����ӂɂ��ƂÂ��ʉݓ��ǂ����߂��~�ϓ����̏���ł���O�Z��~��Z�K�ɒ���t�����܂ܐ��ڂ����B�ʉݓ��ǂ͖����s�������A����N�㔼�̃h�������͘Z�Z���h�����������Ɛ��肳��Ă���[46]�B
���O�N�ɓ���ƁA�C�^���A������A�X�C�X��t�����Ȃǂ͓�d���ꐧ�������͕ϓ����ꐧ�Ɉڍs�C��v�������{�C���ƁC�I�����_�݂̂��Œ葊�ꐧ���ێ����Ă����B�ꌎ���̎���N�č��f�Վ��x�Ԏ��啝�����̕ŁA��ĂɎ�v���B�ʉ݂��}���A�Ēʉݓ��ǂ����N�U��̃h����������ɉ�������B���{�~�͎���N����玵�O�N�ꌎ�܂ŁA�ϓ����̏���߂��Ŏ���������Ă������A�ɓ���C�}���N�ȂǂƋ��ɉ~�������͂��}���ɍ��܂����B�ʉݓ��ǂ́A����������܂ł̔�������ɁA�s��̒����o�����̋㊄�ɑ���������`��h������������B�h���̐敨�f�B�X�J�E���g���́A�X�~�\�j�A������Ō�̓��̓���ɂ͓�l���ɒB�����B
���{���{�͓�Z���ɁA��O���܂ł̓����s��̕��\�C��O���̕č����{�ɂ��ăh���̑r�c�q������Z���؉������\����C��l������ϓ����ꐧ�ֈڍs���邱�Ƃ\�����B�s��ĊJ����������A�~���ɗU�����悤�Ƃ������͊ώ@���ꂸ�A���ʓI�ɉ��B�̒ʉ݊�@�̔g�y��Ƃ�鎖���ł����B
���B�ł̓h�C�c�E�}���N�ȂNj��A�r�c�q�ɑ��镽�����ێ����Ă����ʉ݂��܂ߔ������E�����C�O����������Ńh�C�c�A��͎s��ő�̓�܁`���h���̃h������������s�����B�O������ȍ~�A���{�Ɖ��B�̈ב֎s�ꂪ������A�X�~�\�j�A���̐��͕����B�����Ɏs��͍ĊJ���ꂽ���A���ƁA�t�����X�ȂǘZ�����͑h�������t���[�g�����Ƃ�A���̑���v�ʉ݂͒P�ƃt���[�g�s���邱�ƂƂȂ����B
�s�����̏�
���O�N��Z�`��O���ƎO����`��Z���̓��̎s������Ԃɂ͂��܂ꂽ�A��l���`�O������̈�l������̊ԁC�~�͉��B�ʉ݂ɐ�삯�ĕϓ����ꐧ�ɓ������B�ϓ������̓�l���ɂ́A���S���[�g�͓�~��Z�K�A���̌��Z�O�~�Ȃ�����Z�܉~��A���ɂ͓Z�~�A�ēx�̎s����O���ɂ͓�Z���~�ł������B
���̊ԁC�ʉݓ��ǂ͕ϓ����ꐧ�ڍs�̏����ɓh���̃h����������A����ڂɂ͓�Z�܉~�O�Z�K�ʼn���C�O���ɂ͓�Z�O�~�Ńh�����x�����Ƃ�����B�����Ɏ����v���Ńh�����}������ƁA���ɂ͓Z�~�Ŕ����������B���������ăN���[����t���[�g�Ƃ͒������C��̂̐؏グ����z�肵������Ɛ������ꂽ�B
�����͒Z�������ړ���敨����͋K������A�����ْ����͐�����Ă����B�A�o���Ɋւ�郊�[�Y�E�A���h�E���b�O�Y�ɂ�铊�@�͉\�Ƃ��Ă��A�����̈ב֑���̗\�z���s�m���Ȃ̂ŁC�s��̎��͂��̈��艻�@�\�����邱�Ƃ͂ł����A�ْ�ɂ�钼�惌�[�g�̕������͕s�\���ł������B���������Ĉב֑���̌���Ԃ̈ב֎����Ɉς˂�Ƒ傫�ȕϓ��ށB�����Ō��d�Ȉב֊Ǘ��̉��ł́C���ǂ͎s������������Ȃ��B�N���[����t���[�g�́A�ב֊Ǘ������R�����ĉ\�ƂȂ�B���������h�l�e��������O�Z���A�X�~�\�j�A������[�g�����Z���ȏ���~���ƂȂ��������ł́C�f�Ս����������Ӑ}�����_�[�e�B��t���[�g�Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����̂��Ó��Ȍ����ł��낤[47]�B
�j�N�\���V���b�N��̎b��I�ϓ����ꐧ�ڍs�Ɣ�ׂāC��r�I�e�͓I�Ȑ���^�c���s�Ȃ����w�i�ɂ́A�@��b�I�s�ύt������Ƃ��ɂ́A�Œ葊��ɌŎ����Ė��������ł��Ȃ��Ƃ̔F�����A�ʉݓ��ǂɍ��܂������ƁA�A�O��̕s���ɂ���ׁA����͌o�ς��㏸�ߒ��ʼnߏ藬���������O���ꂽ�Ƃ����}�N���o�Ϗ̑��Ⴊ����B
�O�\�O�@�ϓ����ꐧ�ڍs����Ζ���@�u���܂�
���O�N�O�������ɓ����ב֎s�ꂪ�ĊJ����A�Ζ���@���u�����钼�O�̋㌎���܂ł̈�O�Z���̎�������C���B�ʉ݊�@�Ȃǂ̉e�����������������~�h����������͓�Z�l�`��Z�Z�~�̋������̒��ŕϓ������B����͕ϓ����ꐧ�ڍs�サ�炭�s�������T�邽�߂ɗl�q����������C����Ɋ�ċ��h�l�e�������O�ܥ�����A�X�~�\�j�A������[�g����Z���オ������Z�܉~�𒆐S����Ƃ��ď㉺��E��܁��̕ϓ�����ݒ肵�A���ǂ̓O�ꂵ���s�����ɂ���āA���͈̔͂Ɏ��߂�w�͂������ƌ�����B
�~���̉e���ŁC���O�N�̍��ێ��x�͂i�J�[�u���ʂ̏I���A���[�Y�E�A���h�E���O�Y�̊����߂��A���{���o�����Ȃǂ������āA��b���x�A�������x�͋��z�̐Ԏ��ƂȂ����B�ʉݓ��ǂ͓O�ꂵ���h���̔��������s�Ȃ����B���̊z�͎O������㌎���܂ł̎������Ōܓh���Ɛ��肳��Ă���B
�ϓ����ꐧ�ڍs����ɏo���������ꂪ�A�����̋ύt����ƐM���闝�R�͖R�����C�����炩�Ɋ����̂��̑���ɓ��ǂ��Ŏ������͉̂��̂��B
�@���ۓI���̓I�ł������~�̉ߏ��]����ԁA���ێ��x�啝������ԂɏI�~����ł��A�������x�Ԏ��ɂ���ėݐς����O�݂����炷�C�A���O�N���ȗ��C���t�����������������̂ŁA�A�������������C�h���������ɂ��}�l�^���[��x�[�X�̎��k���ʂ��˂炤�A�B���ێ��x������͕������A�~�����Č�����̂ʼnߑ�]���͏C�������Ȃǂ̌����ǂ�����Ă������ƂȂǂ��w�E����Ă���[48]�B���������̍��ێ��x���ʂ��͌���Ă����B���{�o�ς͎���N�㔼����i�C���}���ɏ㏸�A�C���t�����i�s�A���Տ������������Ă���A�Ζ���@�����ȑO�ɍ��ێ��x�͋��z�̐Ԏ��ƂȂ��Ă����̂ł���B
�l�@�ב���̕]��
�@
�l�\��@�o�ϊw�I�ȕ]��
�@���̊Ԃ̈ב���ɂ������ẮA���{��o�ϊw�҂����́A�ȉ��̂悤�Ȍ������ᔻ�������Ă���[49]�B
�i��j�j�N�\����V���b�N��̈ב֓��ǂ̑Ή��́A���ےʉݏ�ɑ��闝���̐A�ב֊Ǘ��̌��ʂ̉ߐM�f������̂ł���A���̐������f�͢���ۋ��Z����j��ޗ�̂Ȃ����룂ł���A���ۓI�ɂ����I�ȍs���ł������B
�i��j���O�`���l�N�̑�C���t���̐ӔC�̊������́A����ȑO�̈ב���̎��s�ɂ���B�����Ƒ����~�̐�グ�������͕ϓ��ב֑��ꐧ�ڍs��i�߂�ׂ��ł������B
(�O)���O�N�O������㌎�܂ł̎������Ԃɂ킽��h������ŁA���牭�~�ɏ���c��ȃL���s�^������X�������Ɛ��肳���[50]�B�h��������������������Ƃ����s���艻�I���@���s�Ȃ��āC�s�ꑊ��̕ϓ���傫�����������ƂɂȂ�B
�i�l�j�ϓ����ꐧ�ڍs����C�Œ葊�ꐧ�ɋ߂��ב�����Ƃ葱���A�܂����O�N�O���Ɉב֎s�ꂪ�ĊJ�����Ƃ��̉ߑ�]�����ꂽ������ێ����āA�ݐς����h���̊җ����}���������B�ނ���ב֊Ǘ����ɘa���A���摊�ꂪ���X�̍��ێ��x�C�ב֎����A�s��Q���҂̗\�z�f�ł���悤�ɂ��ׂ��ł������B
�l�\��@�����o�ϊw�I�ȕ]��
�@�{�M�̈ב���Ɋւ��鐭���o�ϊw�I�ȕ]���́A�o�ϊw�I�Ȃ���ɔ�ׂđ�܂��Ȃ��̂ƂȂ炴��Ȃ����̂́A�č��̃C�j�V�A�e�B�u�ɑ��āC�I�ɔ�������{�M���ǂƂ����\�}�̒��ł́C�܂��j�N�\���̐V�o�ϐ���Ɏn�܂�l�@�Ώۂ̊��Ԃɂ�����č��̐헪�̐��ڂ�S�̓I�ɔc��������ŁC����ɂ�������{�M���̏��s��̂̔����Ƃ����̑��ݍ�p���A�ב���̎���ł���ʉݓ��ǂ̍s�����ǂ̂悤�ɋK�肵������Օt����K�v������B
�i��j�č��̐헪�Ƃ��̐���
�j�N�\����V���b�N�ɏے������č��̍��ےʉݐ헪�̔w��ɂ́A�ǂ̂悤�ȍs��̂��A�����Ȃ铮�@�ōs��������̌`���ɉe����^���A�܂����̐��ω��𐋂����̂��낤���B�q��[�����]�́A�Љ�I���͊W���p���[�E�G���[�g�_�Ɉˋ����āA���̐��ڂ��ȉ��̂悤�ɕ`���Ă���[51]�B
�����̕č��̒n�ʂ́A���|�I�ȌR���͂ƌo�ϗ͂ő��҂̒ǐ����������A�����w�i�ɔe���V�X�e�����\�z�����B�����ł͕č��͐��E�̒�����s�A���R�f�Ղ̐��i�ҁA�����Ē��S�I�Ȑ��Y�҂ł���A�ē҂Ƃ��ău���g���E�b�Y�̐��Ȃǂ̚��ۃ��W�[���̍\�������o�[�̃��[������������ł����B
���̊J�n�Ő��E�͓�ɉ����A�č��͐����w�c�ɂ����鍑�ی������̋����҂Ƃ��Ă̖�������p���������A�����Ƃ̔e�������Ɛ��E�I�K�͂̉���ɂƂ��Ȃ��R�X�g�ō��͂��ቺ�����B���Ȃ킿�C���t���ƃx�g�i���푈�̐���C�J�����Y���ቺ�ɂ���͎Y�Ƃ̋����͒ቺ�ȂǕč��̌o�σt�@���_�����^���Y�͗��A�h���̉ߑ�]���ŁA����N�ɓ�Z���I�ŏ��߂Ėf�ՐԎ����v��A�������͑ΊO�������̌ܕ��̈�ȉ��ɗ������݁A���ےʉݕs�����p�����邱�ƂɂȂ����B
�����ŕč��͔e���V�X�e�����ێ�����R�X�g�����ɕ��S�����߂�悤�ɂȂ�B���̕\�ꂪ���R��`���E�̌x�@���Ƃ��Ă̖�������k������Ƃ������Z��N�̃j�N�\���E�h�N�g�����ƁA����N�̢�V�o�ϐ�����ł������B����͔e�����Ƃ����s��̂��A����Ȋ��̒��Ŏ��R��`�w�c�̎w���҂ł��葱����u���z�v�ƁA�u���ȑ����v�̖ڕW��Nj�����헪�ł���B
�j�N�\����V���b�N�𓂓˂����j���e�����ȍs���Ɖ��߂���������������C���ۂɂ͎s��̌x���ɔ������������ȁC�e�q�a�̍����B��������������ʉݒ����̐���\�z���������Ă����B����N�܌��̒ʉ݊�@���_�@�ɁA�����ȍ����ɂ�菀�����ꂽ����Ă����ƂɁC�R�i���[���������C�o�[���Y�e�q�a�c���A�{���J�[���������炪���c���d�˂č��肳��A���{�̃^�C�~���O���v���Ă����̂ł���A�ˑR�̑[�u�ł͂Ȃ������B
���l�ȍs��̗̂��v��\�ł���A�M�c��̗��@�o�ύ����ψ�����A�哱�I�������ʂ��B�܌��̒ʉ݊�@��C�c��ł͓��{�̗A�o�U���ւ̌x���������܂�C���{�َ��_���䓪�����B���C�X�ψ���ł͘Z���ɋ��[����~�ƕϓ����ꐧ�ڍs�̌��c�Ă��A�����ɂ̓h���؉����𒆐S�Ƃ��������I�ȍ��ێ��x��o���ꂽ�B�����̓j�N�\�������ɐV�o�ϐ���̌J��グ���{�̌��f�𔗂錋�ʂƂȂ����B
�L�͍��E�l�����S�́u�E�C���A���Y�ψ���v���A�ے����ƒʉݒ������܂ލ��یo�ϐ���̊�{�ۑ�Ɛ���Ă��j�N�\���哝�̂ɓ��\�����B���̂悤�ȗl�X�ȍs��̂̓������ɂ݂Ȃ���A����N�̑哝�̑I�����ӎ������j�N�\�������̢���ȑ�����헪�Ƃ��ĐV�o�ϐ����{���ꂽ�ƍl������B
���ЂƂ����[���̂́A���d�ȃR�i���[�H���̓]���ƃX�~�\�j�A�����ӂւ̌o�܂ł���B��v�����ʉݒ����Ɏ�Ԏ�钆�ŁA���E�o�ς̐�s���ɑ���s�����g��C�ی��`�A�u���b�N���ւ̌��O�����܂����B�W���[�i���Y���́A�\�A�C�����ւ̑Θb�H���ւ̓]���ɔ�ׁC�������Ƃ̑Η���ł���Ɣᔻ�����B���ł��E�I�[���X�������]���ɂނ��d�v�Ȗ������ʂ����B�ċ��]���h���̐؉����C�ے����C�o�C�E�A�����J�������̓P�p������B�S�čő�̖f�Ւc�̂m�e�s�b�́A�h���؉����𒌂Ƃ���ʉݒ��������c�����B
�������ł����S�ۏ�C���E�o�ςւ̈��e�������O����L�b�V���W���[�⍲���A�V�����c�����C�o�[���Y�e�q�a�c���������]���𑣂����B�@�h���؉����Ɖے����p�~�őË����C�ꎞ�I�ȑ����Ԓʉݒ����𑁊��Ɏ������ׂ����Ƃ̎咣�����܂钆�C���B�ł̃h���}����j���[���[�N�����s��ł̑�\���Ȃǂ̎s�ꈳ�͂�������Đ����]���ɍ��ӂ�����ꂽ�̂ł���B
�ʉݕs���̐�s���ƕی��`�̊g������O���C�������Ƃ̋������d�����鍑���̏����́A�j�N�\���������̕��h�A�E�I�[���X�̍��ۋ��Z�E�C�m�e�s�b�ɑ�\�����f�ՋƊE�A����琨�͂��ق���c���B�C�����ă}�X�R�~�����d�H���ɌŎ�����j�N�\�������ɋ������͂ƂȂ����B�S�čő�̖f�Ւc�̂m�e�s�b�́A�h���؉����𒌂Ƃ���ʉݒ��������c�����B
���̂悤�ɕč��ł͑��l�ȍs��̘̂A�q�ƑΗ��̊W���Œ�I�łȂ��C���Q�W�̍Ē������e�Ղł���B�ʏ���肪����������̂́A���ۋ����͂̐Ǝ�Ȍʊ�ƥ�Y�Ƃ��O���̗A�o�U���ɔ����ꂽ���ł���A���̌��ʕی��`�I�v�������܂���̂̊������v�����キ�C���S�ۏ��̍l������Z���{�s��̗��Q�f�����s��̂̉e���͂̑���Ō��I�Ȑ����]������r�I�e�Ղȍ\���ł���[52]�B
(��)���{�̈ב���̕]��
�i�P�j�ב֎s�����Ɋւ��鉼���̒�N�Ƃ���Ɋ�]��
�����{�̐����o�ς̓����́C���I�s��̂ł��鐭�}�̒��ŁA���܌ܔN�ȗ���ɗ^�}�Ƃ��Ă̒n�ʂ��߂Ă��������}�̈�}�x�z�̐��̉��ŁC�l�X�Ȏ��I�s��̂ł����ƂȂǂ̗��v�W�c���ʍ����̑����I�ō��������v�������ݏグ�C���ЂƂ̌��I�s��̂ł��銯���@�\��ʂ��Ē������A�o�ϐ����̉ߒ��Ŏ�������_�ɂ������B���̉ߒ��ő��l�ŋ��łȊ������v�������v�W�c���g�D����v�������x�����ꂽ�B���̂悤�ȍ\�����������}�����⊯���g�D�́C�j�N�\���V���b�N�ɍۂ��āC�����̍ĕ��z��������v�̍ĕ҂ɂȂ���ʉݒ����ɑ��Đv���ɑΉ��ł��Ȃ������B�ۊv�Η��̌����C���ĘH���ɗ��������}�̖��i�Ƃ����������A���{������}�����ۋ����H�������ɂ��������B�ʉݒ������ł́C�����}���狤�Y�}�܂ʼn~��グ���A�Œ�ב��x�n��̎p�����Ƃ����B
�@��}�x�z�̉��A������含�������Ă��邱�Ƃő傫�ȍٗʂ��ς˂��A�������ɑ傫�ȉe���͂������Ă���G�[�W�F���g�̒ʉݓ��ǂ́A���ۂɂ͍��ےʉݏ��c������\�͂��s�\���ł���A�I�m�ȏ����W�ƕ��͂̓w�͂�ӂ����B�܂���菈���ɗL���Ȑ���������ł��Ȃ������w�i�ɂ́A�����ɓ��L�Ȏ狌�I�ȍs��������A�Z���I�ȖڕW�̂��Ǝb��I�Ȑ���̒����A��D����u���邱�ƂŏI�n�����B
�@�}�X�R�~���܂߂č������s��̂��ꍑ��`�I�ȑΉ����������ŁC�Εċ�������R��`�s��o�ς��d��������E�A���Ɍo�ϓ��F��́A�~��グ�������Q�̑Η�������Ȃ�����A���E�Ǝ����}�A���������Ƃ̈ב�����߂��钲���ߒ��ŁA�����̖�������ʂ����B�~��������[53]�̌���Ǝ��{�ߒ��A�ϓ����ꐧ�ڍs�ߒ��A���Ėf�Ռo�ύ�����c��̋ǖʂł̉~��グ�e�F�ŁA�������t�̐���Ɍ���I�ȉe����^�����Ƃ����悤�B
�@���E��������グ�_�֓]�������̂ɂ������āC�ʉݓ��ǂ͏��Z�̒肩�łȂ����v��̐����ێ����A�o���邾������ɋ߂��`�ł̌����ɌŎ����A���̂��߂Ɍo�ϓI���������^�킵���s������������{�����B���̊�{�ڕW�́A�����ɂ킽��L�Ăɑ��݂��鏔�s��̂̉~��グ�A�����M�[�����Ă��āA���i�ȊǗ�����ɂ��~���U���Ő�グ����Ⴍ���������݁A���̏�œ��Č��⑽���Ԍ��ɗՂ��A�ǖʂ�ŊJ�ł����Ǘ����������ł���A���ǘH���]����]�V�������ꂽ�B
�ʉݓ��ǁA���E�A�}�X�R�~�ȂǏ��s��̂̑��ݍ�p��T�ς��Ă����������t�́A�R�i���[�K���ɂƂ��Ȃ����Č����s��C���E�o�ς̓����s�����C�ی��`�̑䓪�C�č��ł̐����]���̒����������āA�N�������ւ̕��j��Q���ł߂��B�����̉~��グ�A�����M�[�����É����������B�������@�ی��̓�q�ȂǂƂ��킹�C���{�̈ב���̍d�����͕č��̑Γ��s�M�����߁A���̌�̓��ĊW�ْ̋��Ɍq�������Ƃ����悤�B
�@�����ȃh���~����ɂ��A�o�哱�̌o�ϐ�������̈ێ����A���s��̂ɋ��ʂ̗��v�ł���A���́u���v�v�Ƃ݂Ȃ���Ă����B�ב֑���ϓ��̂����s��̊Ԃ̕��z��̑Η��Ȃǂ͖��Ƃ���Ȃ������B���������������D�揇�ʂ��咣���鐭���o�ϖ�肪�o�Ă���ƁA����v��̍Ē�`���K�v�ƂȂ��Ă���B����ɍ��v���鏔�s��̊ԂɐV���ȍ��ӂ�����������̓]�����s�Ȃ���܂łɂ́A�����x�����S�����Ȃǂ̗��R�Ŏ��Ԃ�������B���̊ԑ傫�ȍٗʂ����ב֓��ǂ́A�s�����œ��O�̏��s��̂̔��������ɂ߂v�����V�p���̐����I���f��҂B���̉ߒ��ŒNj�����̂́A�~���Ƃ����u���v�v�ւ̍v���ɂ��u�����v�Ɓu�g�D�̑����v�ł������B����������͏��F�d��ꂽ������`�̐���̉��ł̋ߎ���I�s���ł���A�������̊l���Ƃ͒��������ʂƕ]������������Ȃ��B
���ێ��{�ړ��̊������Ő��̍��ۑ̐��������ݎn�߁C�V�������ے����ւ̖͍����n�܂������ƁA����Ԋҍ��ӂɂ�������炸�ב֒�����@�ی��Ŋ�łɢ���v����咣���ăj�N�\�������̑������������Γ��s�M�����߂Ă��邱�ƁA�x�g�i���푈�̓D������E���A�W�A�ɂ����鐨�͋ύt�̒�����}��Ē��Θb�ւ̓����Ɍ�����č��̐헪�̃V�t�g�ɂ��ĊO�ǂƂƂ��ɔc�����ăv�����V�p���ɑ����I�Ȑ헪�̍�����������A���̘g���œK�Ȉב����W�J���ׂ��ł������B
�]���Ă��̎����̉������́A���ނ��͂��߂��e���V�X�e���ێ���p���~��グ�̌`�ŕ��S������ꂽ���ʁC���ێ��{�ړ������������͂��߂��ɂ�������炸�ב֊Ǘ����ێ��E�������Ăł��~����������낤�Ƃ������摗��^�A�d����`�^�̕����I�Ȃ��̂ł������Ƃ����悤�B
�i�Q�j�ב։������̕Ό��̗L���ɂ���
�@�ב֎s�����ɂ��ẮA���s��̗̂��Q�W�ɑ傫���e�������ꍇ�������B�ʉݓ��ǂ́A���̖��ɂ��Ă��A�傫�Ȑ����ӔC���Ă���B�j�N�\���E�V���b�N��ɁA���{�̒ʉݓ��ǂ��ב֎s���������ɋ�����Ńh���������Ă������ɂ��Ă��A���Z�E��Y�ƊE�~�ς̈Ӗ����傫�������Ƃ�����B�������ɗA�o�Y�Ƃ�C�^�ƊE�Ȃǂ́A�d���Ȉב֊Ǘ�����ɂ��A�בփ��X�N�̃w�b�W������A�~���ɂ���Q�͑���ł������B
����ɔ�ׂĈ�͑����������K���̉��ɂ���A�ב֍����̋K�͔͂�r�I�����Ă����͂��ł���B���������ǂ͊O������ԍς����ɔF�߂���(����N������Z��)[54]�C�s��̏I�����Ԃ��������Ă܂ň₩��h����������(������)�B�ʉݓ��ǂ����̂悤�ȍs�����Ƃ����̂́A�j�N�\���E�V���b�N�ȑO�ɁA�~�����ێ��̂��߂Ɉ�ɖ����Ƀh����ۗL���������߁A���͂�����ɑ����������Ȃ��Ƃ̈ӌ��������Ă����Ƃ�����[55]�B
���̂悤�Ȉב���́A���D�A�C�^�A���̑��̗A�o�Y�ƂŁA�בփ��X�N�E�w�b�W�̎�i�𐧖�Ă����ƊE�ɂ���ׂāA�ʉݓ��ǂɋ߂������������̂Ɣᔻ����Ă��d�����Ȃ��Ƃ����̂�����̕]���ł���[56]
����ł��A���Ђɂ�鑽�z�ȗA�o�O��������C��̑�ʂ̃h������̓��@���Ȃ�тɒʉݓ��ǂƈ�̖����ɂ��Ă̔ᔻ��_�c���s��ꂽ�B���̒��œ��{��s�̊O�����݂̊����O�ԍϗe�F�C�O�ݗa���̒lj��Ȃǂւ̔ᔻ�Ƌ��ɁC������Z���A���ɂ�����s��ł̑�ʂ̃h�����肪����̎����ɂ����̂Ƃ̋^�f�ň��O���ǒS���������Q�l�l�Ƃ��Ċ��₵���B�a�c�Õv�Q�c�@�c���́A���₪�h������ɂ��Ċe�s�Ԃ̃o�����X���Ƃ邽�߂̗U��������ȂNjٖ��ȊW�������A���ʓI�ɑ��s��古�Ђ̗��v�i��ɂȂ��鐭����s�Ȃ����Ɣᔻ�����B�����ᔻ�ɑ��č����͓��ǂ̍s����ٌ삵�A�c�_�͕��s�������ǂ邱�ƂŏI�����[57]�B
�i��Z�Z�O�N��Z����Z���@�����j
�@
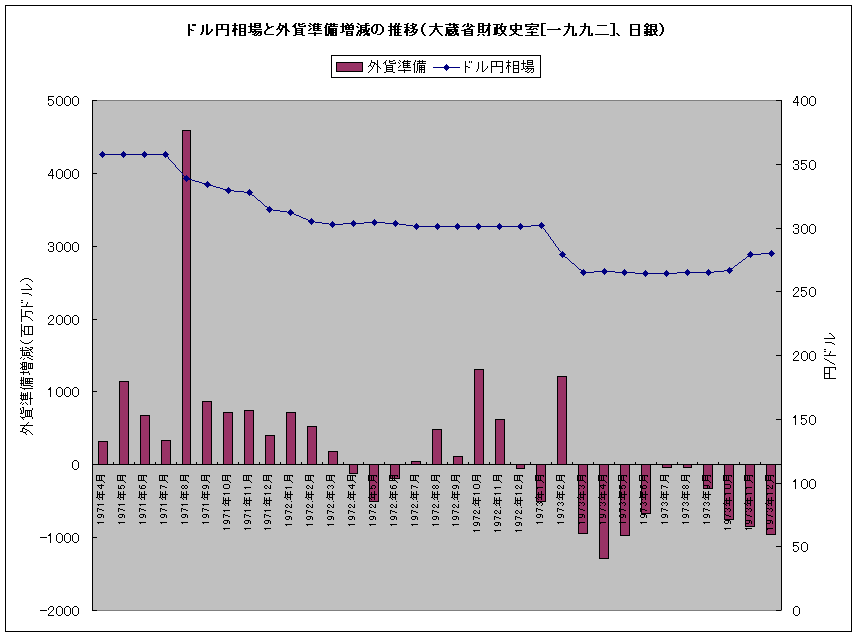
�Q�l����
De Grauwe,P., International Money, Oxford University
Press, 1996
Dominguez, K.M.,�hCentral bank
intervention and exchange rate volatility�h,
Journal
of International Money and Finance, 1998
Frieden,Jeffry A. & Lake,
David A.ed., International Political
Economy�]Perspectives on Global Power and Wealth, Fourth
Edition, Routledge, 2000
Frieden, Jeffry
A., �gExchange Rate Politics�h., Frieden & Lake[2000]
Galati, G. & Melick W. , Perceived Central Bank Intervention and
Market Expectations: An Empirical Study of the Yen/Dollar Exchange Rate, 1993�\96, Bank for International Settlements,
Working Papers, No.77,October
1999
Gilpin, R., Global Political
Economy�]Understanding the International Economic
Order, Princeton
University Press, 2001
Jurgensen, P., Report of the Working Group on Exchange
Market
Intervention(Jurgensen Report), U.S.Treasury
Department,1983
Sarno,L. & Taylor,M., �hOfficial
Intervention in the Foreign Exchange Market: Is It Effective and, If So How
Does It Work?,�h Journal of Economic Literature, September 2001
Volcker,P. & Gyohten,T., Changing Fortunes, Times Books,1992 �i�|�[���E�{���J�[�A�s�V�L�Y���E�]��Y��Ė�w�x�̋��S�\�~�ƃh���̗��j�x���m�o�ϐV��Ё@�����N�j
�؏��F����쐳���w�o�σV�X�e���̔�r���x���́x������w�o�ʼn�@����Z�N
�����A��w�f���N���V�[�̒鍑�x��g���X�@��Z�Z��N
�l�c�G��u����̕s�ى�����͊Ԉ���Ă���v�A�u�[���������̋��Z����ɂ��o�ω̎�i����v�A��c�K�v�j�ҁw���Z����̘_�_[���E�[����������]�x���m�o�ϐV��ЁA��Z�Z�Z�N
�{�c�h�g�E�`���v�ҁ@�w���ؗY��̏،��E�����{�̍��ۋ��Z�j�x
�@�@�L��t�@���㔪�N
��x���G�@�u�摗�茻�ۂ̕��́v������v�E���쐳���ҁw�����o�u���̌����i���j�x�@���m�o�ϐV��Ё@��Z�Z��N
�ɖ��c���Y�@�O�X���I�@�u�בփ��[�g�Ɠ��ĉ������̔�r�v
�@�@�w���Z�V�X�e���̍\�����@���Z�����Ǖ��@���{���Z�����@�O�x
�@�@�@�@�@���{�o�ό����Z���^�[�@��Z�Z�Z�N��Z��
�����M�q�u�|�X�g�e���V�X�e���Ƃf�V�T�~�b�g�v�����F�E�ɓ����d�E���ꌛ�ҁw���ې����o�σV�X�e���x�L��t�@���㎵�N
�ɓ����q�w�בփ��[�g�Ɨ\�z�`���x���{�o�ό����Z���^�[�A���Z�~�i�[�A��Z�Z��N�ꌎ��Z��
���쒉�u���ےʉ݁E���Z���ւ̐����o�ϊw�I�ڋ߁v�w���l����_�W�x��Z�Z�O�N�O�����
���c���F�@�w�ʉ݊O���x�@���m�o�ϐV��Ё@��Z�Z�O�N
�Ï���q�u�o�u���`�������̔w�i�Ƃ��Ă̓��Čo�ϊW�v������v�E���쐳���ҁw�����o�u���̌����i���j�x�@���m�o�ϐV��Ё@��Z�Z��N
���{�����Y�u�S�S��s�̈ב֥���Z�����_�c�𐳂��v�A�u�����͂���̓���o�b�V���O�v�A��c�K�v�j�ҁw���Z����̘_�_[���E�[����������]�x���m�o�ϐV��ЁA��Z�Z�Z�N
���{�����Y�E�{�c����q�w���㍑�ۋ��Z�_[���j�������]�x���{�o�ϐV����
�@��㔪�O�N
�o�D�q�D�N���O�}���^�l�E�I�u�Y�t�F���h���@�Έ�E�Y�c�E�|���E��c�E�����w���یo�ρ@���_�Ɛ���@�U���ۃ}�N���o�ϊw�x�V���Ё@�����N
�q��_�@�w���Ēʉ݊O���̔�r���́x�䒃�m�����[�@�����N
������v�E����͔V�u�����{�ɂ����鐭����{�F���}�Ɗ����v������v�E���쐳���ҁw�����o�u���̌����i���j�x�@���m�o�ϐV��Ё@��Z�Z��N
�������u���ۃV�X�e���̕ϗe�Ɠ��{�̃o�u���v������v�E���쐳���ҁw�����o�u���̌����i���j�x�@���m�o�ϐV��Ё@��Z�Z��N
���{��s�S�N�j�Ҏ[�ψ���ҁw���{��s�S�N�j��Z���x���{��s�@��㔪�Z�N
������w�o�Ϙ_��\���܂����ɂ����@�̋����Ǝ����x�@���{�]�_�Ё@��Z�Z�O�N
�呠�ȍ����j���ҁw���a�����j�@���a�`�l���N�x�@���@���ۋ��Z�E�ΊO�W�����i�Q�j�x���m�o�ϐV��Ё@�����N
���M�Y����ˏd�T�u��s�ى�����_�̢���o��v�A��c�K�v�j�ҁw���Z����̘_�_[���E�[����������]�x���m�o�ϐV��ЁA��Z�Z�Z�N
��䏺�v�@�w���Čo�ϖ��C�Ɛ����x�L��t�@����Z�N
��{�����Y�@�w���Ɗw�̂����߁x�����ܐV���@��Z�Z��N
�����@�v�@�u�O���ב։���̕]���v�w���{���ƁE��s����̐M�p�́@���Z�����Ǖ��@���{���Z�����@�Z�x�@���{�o�ό����Z���^�[�@��Z�Z��N�O��
�|�������@�w���Ė��C�̌o�ϊw�x�@���{�o�ϐV���Ё@����O�N
�˖�N�N�w���Z�r�b�O�o���̐����o�ϊw�x���m�o�ϐV��@��Z�Z�O�N